ERPの運用フェーズで差がつく業務改善の見える化手法
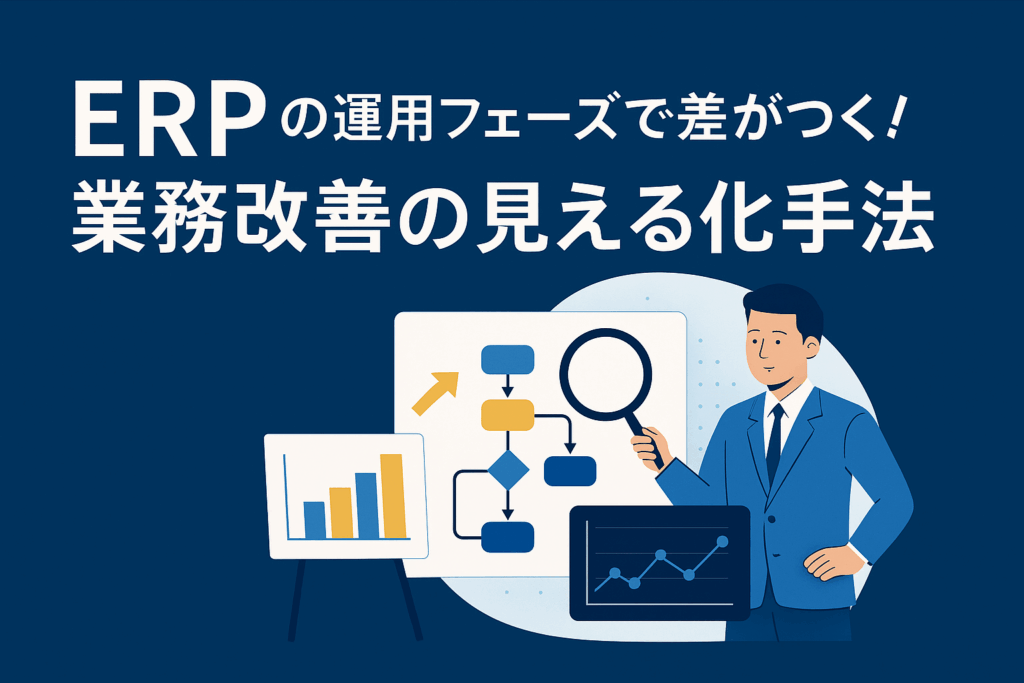
はじめに
ERP(基幹業務システム)を導入すれば、業務効率化は自動的に進む――そう考えていた時期が、あなたの組織にもあったのではないでしょうか。しかし現実には、導入後の運用フェーズこそが真価を問われる場面です。システムは稼働しているのに、属人的な判断が残り、場当たり的な対応が続く。そんな悩みを抱える企業は少なくありません。
本記事では、ERP 業務可視化という視点から、データに基づく継続的な改善サイクルをどう回すかを解説します。KPI(重要業績評価指標)やSLA(サービス水準合意)を確実に達成し、効果創出までの道のりを最短化するための考え方をお伝えします。
なぜERPの運用で差がつくのか
ERPシステムは、導入時の設計と運用時のデータ品質によって成果が大きく左右されます。多くの企業では、システムから日々蓄積されるイベントログ(業務の発生記録)が各部門に分散し、全体像を把握しづらい状態にあります。
受注から入金までのプロセス(O2C:Order to Cash)や、調達から支払までのプロセス(P2P:Procure to Pay)といった基幹業務を横断的に分析しようとしても、データがサイロ化していて困難なケースが多いのです。ダッシュボードでKPIの結果は見えても、「なぜそのズレが生じたのか」という原因までは見えにくい。結果として、ボトルネックや手順のばらつき(バリアント)は放置され、規定手順との適合性チェックも形式的になりがちです。
よくある課題のシグナル
リードタイムが月によって20%以上も変動する。在庫と需要予測が乖離してキャッシュフローが圧迫される。SLA逸脱の再発要因が、いつも「担当者の個人差」で片付けられてしまう――。これらは、ERP 業務可視化が不十分なために起こる典型的な兆候です。
プロセスマイニングがもたらす解決策
ここで登場するのが、プロセスマイニングという技術です。ERPや周辺システムに蓄積されたイベントログを統合し、実際に行われている業務フローを客観的に再構成します。
従来のダッシュボードが「結果」を示すのに対し、プロセスマイニングは「経路」と「待ち時間」を可視化し、ヒートマップで業務の詰まりを明らかにします。規定手順との適合性分析、ボトルネックの特定、手順のばらつき比較、さらにはAIを活用した予測や改善提案まで、一貫して実現できる点が特徴です。
従来の分析手法との違い
プロセスマイニングは、ログに基づく客観性、粒度の柔軟性、運用への組み込みやすさで従来手法と一線を画します。RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)やオーケストレーションツールと連携することで、問題の検知から是正までを自動化できます。
詳しくはプロセスマイニングとはのページをご覧ください。
実際にどんな効果が期待できるのか
国内外の製造・流通・サービス業の事例では、O2Cプロセスでリードタイム短縮が15〜35%、P2Pプロセスで例外処理の削減が20〜50%、在庫回転率の改善が5〜12%といった実績が報告されています。
承認待ちの滞留を可視化してO2Cプロセスの待ち時間を25%短縮した例や、支払照合業務の自動化率を30〜60%まで引き上げた例、在庫差異を40%低減した例など、継続的な可視化と改善サイクルにより成果が生まれています。AI(人工知能)による異常検知や、デジタルツインを使った改善シナリオの事前検証も活用されています。
AIを活用した分析機能については、AI分析と改善提案のページで詳しく紹介しています。
導入から活用までの実践ステップ
成功のカギは、「小さく始め、速く回し、広げる」というアプローチにあります。
ステップ1:対象プロセスの選定とデータ準備
まずはO2CまたはP2Pのいずれか、最も改善効果が期待できる単一プロセスを選びます。ERPと周辺システムからイベントログを抽出し、ケースID、タイムスタンプ、アクティビティといった基本要素を標準化します。
データ品質の早期是正が重要です。この段階で現場と一緒にデータの意味を確認し、KPI定義を共通化しておくことが後の成功を左右します。リアルタイムデータ連携の仕組みを整えることで、継続的なモニタリングが可能になります。
ステップ2:分析設計と可視化
PQL(Process Query Language)と呼ばれるプロセス専用のクエリ言語を使って、手順のばらつきや遅延要因を抽出します。単に「遅い工程はどこか」を見るだけでなく、「なぜ遅いのか」という因果関係を掘り下げることが重要です。
可視化ツールの活用法については、プロセス可視化ツールのページをご覧ください。
ステップ3:改善の実装とフィードバックループ
分析結果を踏まえて、具体的な改善策を実装します。RPAで反復作業を自動化したり、業務ルールを見直したり、アラートの閾値を設定したり。重要なのは、フィードバックループを設計することです。
このサイクルを3か月程度で一周させることで、現場の納得感も高まり、次の改善テーマへとスムーズに移行できます。可視化から実行までの流れについては、こちらで詳しく説明しています。
ステップ4:ガバナンスの確立と横展開
改善が軌道に乗ったら、例外処理の定義、承認経路、アラート発報の条件などを明文化し、監査ログを保持する体制を構築します。一つのプロセスで成果が出たら、他のプロセスへと水平展開していきます。
導入プロセス全体の流れは、導入プロセスのページで網羅的に解説しています。
成功のための重要ポイント
データ品質の早期是正、現場による指標定義の共通化、オブジェクトセントリックな設計が成功の鍵です。注文、仕入、配送といった複数のオブジェクトの関係性を正しく扱うことで、より実態に即した分析が可能になります。
ROI(投資対効果)は、短期的にはリードタイム短縮による受注消化量の増加や在庫圧縮による資本コスト削減、長期的には再発防止による工数削減や標準化による教育コスト低減で測定します。
よくある質問
Q1. ERPの標準レポートと何が違うのですか?
標準レポートは集計結果を表示するものですが、プロセスマイニングは経路・待ち時間・分岐(バリアント)を可視化します。規定手順との差異や問題の再発リスクまで示し、ERP 業務可視化として日次で運用すれば、現場の意思決定がデータ主導に変わります。
Q2. データが整っていないのですが、始められますか?
はい、始められます。データの不備を発見し是正することも、プロセスマイニングの重要な役割です。初期段階での不安は、ディスカバリーワークショップで専門家に相談できます。無料で要件の壁打ちや初期ベンチマークづくりを行えます。
Q3. 一度導入したら、あとは自動的に改善されますか?
プロセスマイニングは、改善のための「見える化」と「気づき」を提供するツールです。実際の改善は現場主体で進めますが、RPAと組み合わせることで発見した問題の是正を自動化できます。導入後のサポート体制については、サポート体制のページをご確認ください。
まとめ:データが示す改善の道筋
ERP 業務可視化は、KPIやSLAの達成を「偶然」から「再現性」へと変える運用基盤です。完璧を目指して足踏みするのではなく、小さく始めて速く学習し、成功体験を積み重ねながら横展開していくことが重要です。改善のための設計図は、すでにあなたの組織のシステムに蓄積されているデータの中にあります。
次の一歩を踏み出しませんか
まずは、O2CまたはP2Pのいずれか一つのプロセスを選び、イベントログの取得可能性とKPI定義を1週間で棚卸ししてみましょう。
具体的な進め方はCelonisの導入事例や導入プロセスのページで紹介しています。無料のディスカバリーワークショップを活用すれば、90日以内に改善の初回リリースと運用最適化のサイクルを立ち上げることが可能です。
プロセスマイニングの導入や活用についてのご相談は、お問い合わせページからお気軽にどうぞ。あなたの組織の課題に合わせた最適なアプローチを、一緒に考えていきましょう。


