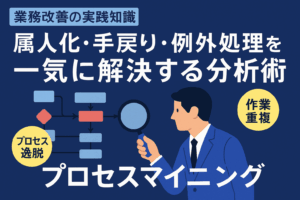複数部門にまたがる業務を一貫して可視化するには?|プロセスマイニング全体最適化の実践ガイド
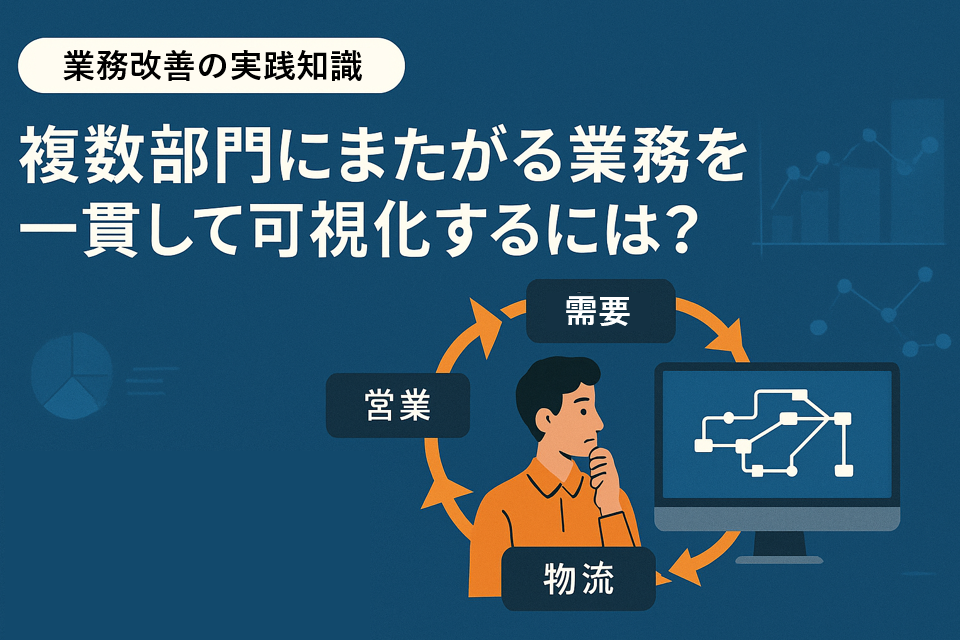
部門間の断絶が生む非効率、どう解消するか?
企業の成長とともに業務は複雑化し、営業、購買、物流、カスタマーサポートなどの各部門がそれぞれ異なるシステムや手法で業務を遂行するようになります。しかし、こうした「縦割り構造」は、情報の断絶や重複業務、プロセスの非効率を引き起こし、結果として顧客体験の悪化や利益率の低下につながります。
このような課題を根本的に解決する手法として、いま注目されているのが「プロセスマイニングによる全体最適化」です。特にクロス部門のプロセス統合や、次世代技術であるオブジェクトセントリックプロセスマイニング(OCPM)が、従来の改善アプローチでは見えなかった課題を明らかにし、大きな効果を生み出しています。
なぜ「全体最適」がこれほど重要視されるのか?
部分最適の限界と組織的な混乱
従来の業務改善は、各部門単位で行われることが一般的でした。購買部門では発注サイクルの短縮、営業部門では成約率の向上といった個別の改善が進められます。しかし、部門間の連携が取れていない場合、このような個別最適化が他部門の業務を圧迫し、全体では非効率が悪化するという"改善の逆効果"が発生します。
実際、経済産業省の「DXレポート」においても、レガシーシステムによる情報の分断がもたらす企業経営への深刻な影響について警鐘を鳴らしており、多くの企業が直面している現実的な課題となっています。
データ連携の重要性と従来手法の限界
部門をまたぐ業務フローでは、同じ案件であっても営業システム、ERPシステム、物流システムなど複数のシステムで情報が分散管理されています。従来の改善手法では、これらのシステム間のデータ連携状況を正確に把握することが困難で、「どこで、なぜボトルネックが発生しているのか」を客観的に特定できませんでした。
プロセスマイニングがもたらす部門横断の可視化
クロス部門の業務フローを客観データで再構成
プロセスマイニングは、部門を超えて業務プロセスを「イベントログ」という客観的データから再構成し、可視化する技術です。ERPやCRMなど複数のシステムにまたがるデータを統合し、「顧客からの受注→製造指示→出荷→請求→入金確認」といった全体のプロセスフローを一気通貫で把握できます。
従来の業務フロー図は現場の記憶や推測に基づいて作成されることが多く、実際の業務と乖離していることが少なくありません。一方、プロセスマイニングでは実際のシステムログから業務の流れを再現するため、「実際はどこでどのような業務が行われているのか」を正確に把握できます。
リアルタイムでの問題発見と改善機会の特定
プロセスマイニングツールは、業務の実行状況をリアルタイムで監視し、通常とは異なるパターンや遅延が発生した際に即座にアラートを発信する機能を備えています。これにより、問題が深刻化する前に対策を講じることが可能になります。
新しい潮流「オブジェクトセントリックプロセスマイニング(OCPM)」とは?
従来手法を超える多角的な分析
従来のプロセスマイニングは「ケース単位」、すなわち一つの案件の流れを追跡することが中心でした。しかし、実際のビジネスプロセスでは、注文、請求書、顧客、製品など複数のオブジェクトが複雑に関連し合っています。
OCPMは、これら複数のエンティティを同時に分析する革新的な手法です。例えば、「なぜ一つの注文に対して複数回の請求処理が発生したのか」「特定の顧客において承認プロセスが長期化する要因は何か」といった、従来では見えなかった因果関係を明らかにできます。
Celonisによる実践的なOCPM活用
業界をリードするCelonisプラットフォームでは、OCPMに対応した高度な分析機能を提供しています。複数部門のデータを統合し、プロセス全体の動的な関係性を視覚化することで、クロス部門での意思決定スピードを劇的に向上させています。同プラットフォームは、ガートナー社の「Magic Quadrant for Process Mining Platforms」において2年連続でリーダーポジションに認定されており、その技術的優位性が第三者機関からも評価されています。
クロス部門プロセス改善の実践ケース
製造業における発見:問題の根本原因は予想外の場所にあった
年商500億円規模の製造業A社では、当初購買部門の納期遅延が課題と考えられていました。しかし、プロセスマイニングによる全体分析を実施した結果、実際のボトルネックは営業部門の承認フローにあることが判明しました。営業担当者から営業部長への承認申請において、案件の優先度判断に時間を要していたことが、全体の納期遅延を引き起こしていたのです。
全体プロセスを可視化したことで、営業部門の承認基準の明確化と、優先度判断のためのダッシュボード導入を実施。結果として、受注から出荷までのリードタイム全体を15%短縮することに成功しました。
小売業における属人化の解消
年商300億円の小売業B社では、部門間の引き継ぎプロセスにおいて、メールや電話による確認業務が属人化していました。特に繁忙期においては、担当者の経験と勘に依存した業務フローが多く、新人教育にも時間を要していました。
プロセスマイニングツールの導入により、これまで見えなかった引き継ぎパターンと所要時間を定量化。標準的な業務フローの確立と、例外処理のためのエスカレーション・ルールを策定しました。結果として、部門間の連携時間を30%短縮し、顧客対応品質の向上も実現しています。
結論:クロス部門の全体最適化には「データドリブンなプロセス改革」が不可欠
複数部門にまたがる業務の最適化には、従来の属人的な業務フロー改善ではなく、客観的なイベントログに基づく科学的な可視化が不可欠です。プロセスマイニング、特にOCPMのような先進的な手法を活用することで、全体のプロセスを俯瞰しながら、具体的で実効性の高い改善アクションを実行できます。
企業の競争力向上において、部門間の連携最適化は避けて通れない経営課題です。データに基づく客観的な現状把握から始まる改革アプローチが、持続的な業務改善の基盤となるでしょう。
関連リンク: リアルタイムデータ連携による業務可視化について → https://flr-process.com/celonis/linkage/
Q&A:よくある質問
-
OCPMと従来のプロセスマイニングの具体的な違いは?
-
従来手法は一つの案件(例:一つの注文)の流れを追跡するのに対し、OCPMは注文、請求書、顧客、製品など複数のオブジェクト間の関係性を同時に分析できます。これにより、「なぜこの顧客の案件だけ承認に時間がかかるのか」といった、より具体的で実用的な洞察を得られます。
-
導入効果を実感できるまでの期間は?
-
限定的なプロセスでのPoC(概念実証)であれば、2〜3ヶ月で初期効果を確認できます。全社的な展開を含めた本格運用では、6〜12ヶ月程度で明確な投資対効果を実感できるケースが多いです。
今すぐできる一歩
貴社でも部門横断での業務可視化と最適化をご検討であれば、まずは無料のディスカバリーワークショップをご活用ください。現在の業務構造を専門家と一緒に分析し、プロセスマイニング導入の可能性と期待効果をご提案いたします。
▶ 詳細はこちら → https://flr-process.com/discovery-workshop/
年商100億円以上の企業様を対象とした実績豊富なコンサルタントが、貴社の課題に合わせた最適なアプローチをご提案いたします。部門間の非効率にお困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。