プロセスマイニングで「手戻りコスト」の削減に挑む方法
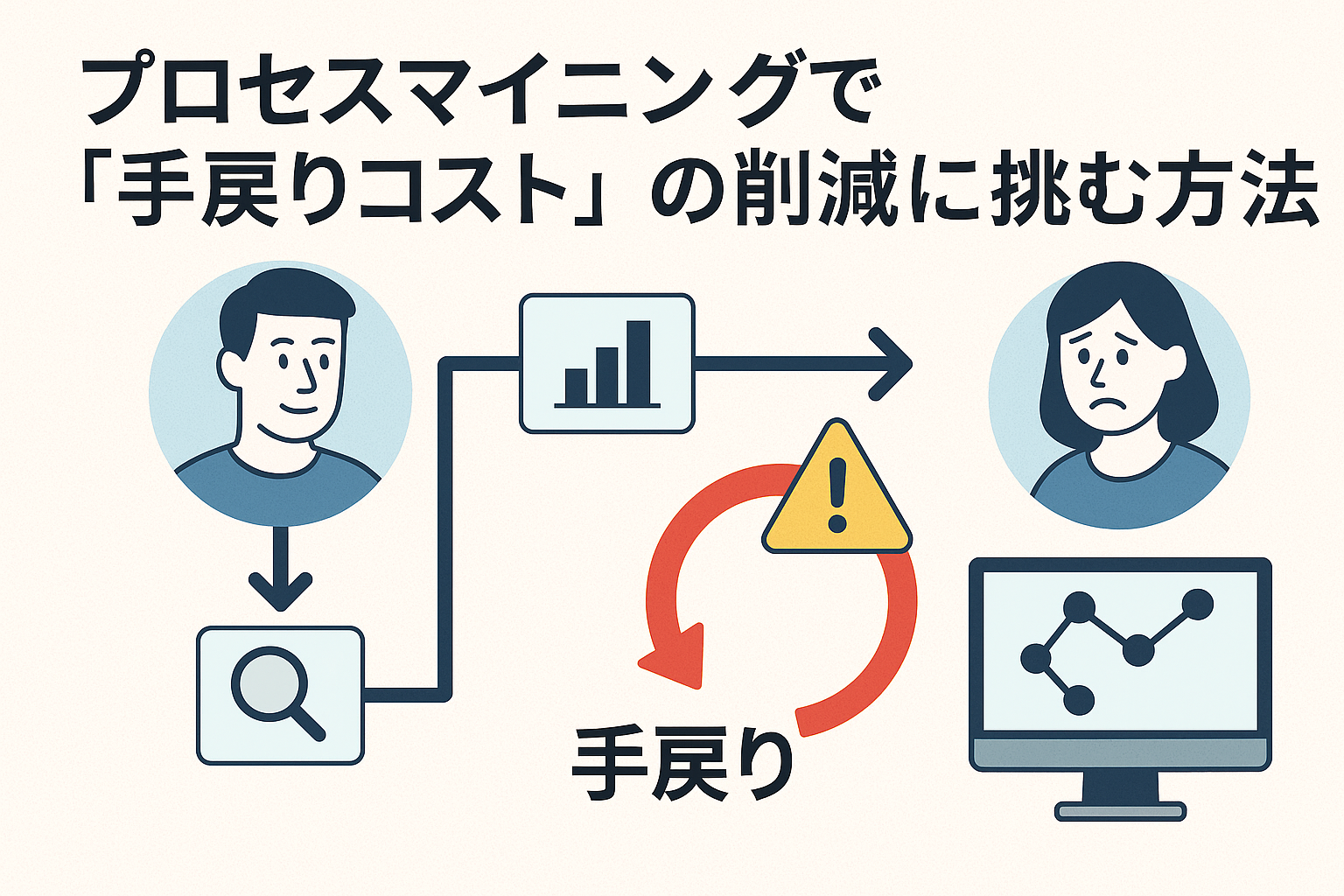
なぜ「手戻り」はいま注目されるのか
「せっかく作った成果物が差し戻される」「同じ業務を何度も繰り返している」――こうした"手戻り"現象は、多くの企業で日常的に発生しているにもかかわらず、長らく「業務の性質上仕方がない」ものとして見過ごされてきました。しかし、近年では この手戻りによるコスト損失が、企業の競争力に与える影響が深刻視されています。
経済産業省の「DXレポート2」では、レガシーな業務フローや属人化がボトルネックとなっていると指摘されており、再作業(リワーク)や流れ逸脱による非効率性が大企業の成長を阻害する要因として明記されています。わずかな非効率の積み重ねが機会損失につながるケースも少なくありません。
この課題の解決に向けて、いま企業が注目しているのが「プロセスマイニング」という手法です。従来の主観的な業務分析とは異なり、システムログから実際の業務フローを客観的に可視化し、手戻りの根本原因を科学的に特定できる技術として、急速に導入が進んでいます。
プロセスマイニングとは:"見えない手戻り"をデータであぶり出す
プロセスマイニングとは、ERP(基幹業務システム)やCRMなどの業務システムから取得される「イベントログ」を分析し、実際に行われている業務プロセスを自動的に可視化・分析する手法です。
一般的な業務分析手法と比較して、プロセスマイニングには以下のような特長があります:
- 再作業や差し戻しの頻度を正確に測定できる
- 理想的なプロセスからの逸脱パターンを自動抽出できる
- 属人的な解釈を排除し、客観的な意思決定が可能になる
たとえば、請求処理のプロセスで「請求書作成」→「承認」→「送付」という標準フローがあるとします。しかし実際には、特定の部門や担当者において「承認差し戻し」が頻発していたり、「修正・再作成」のループが発生していたりするケースがあります。プロセスマイニングでは、こうした流れ逸脱や再作業パターンを自動的に検出し、定量的に可視化することが可能です。
Celonisをはじめとする最新のプロセスマイニングプラットフォームでは、手戻りの発生パターンを明確に把握できる分析テンプレートが用意されており、どの工程で、どの程度の頻度で手戻りが発生しているかを瞬時に把握できます。
実例に学ぶ:手戻り削減のインパクト
ケース1:製造業A社
「検査→修正→再検査」というループが頻発していたA社では、プロセスマイニング導入後、品質管理工程における再作業の割合を38%から12%に削減。年間で約8,000時間の作業工数を削減し、品質向上と同時にコスト削減を実現しました。
ケース2:金融業B社
ローン審査プロセスでの「入力ミスによる再確認」が多数発生していたB社では、プロセスマイニングによる分析結果から入力フォームの仕様変更とルールチェック強化を実施。平均対応時間を27%短縮し、再作業率も45%から18%に大幅に低下させることに成功しました。
ケース3:小売業C社
発注業務において「在庫確認不足による発注キャンセル」が頻発していたC社では、プロセスマイニングにより在庫連携のタイミングに問題があることを特定。システム連携の最適化により、発注プロセスの手戻り率を60%以上削減しました。
これらの事例に共通するのは、「経験と勘」では発見できなかった手戻りの根本原因を、データに基づいて特定できたという点です。
専門家はこう語る:「手戻り」の正体とは何か
プロセスマイニングの創始者として知られるRWTHアーヘン工科大学のWil van der Aalst教授は、「手戻りや逸脱は、システム上では見落とされがちな現象だが、企業の隠れた非効率を表す最良の指標である」と述べています。
また、『Process Mining Manifesto』では、"逸脱検出"はプロセスマイニングの3大機能(プロセスディスカバリ、適合性チェック、プロセス拡張)の一つと位置づけられ、特に再作業に伴うコスト増加への警鐘が鳴らされています。
国内の業務改善専門家も、「手戻りコストは『見えないコスト』の代表例」として、その可視化の重要性を指摘。従来の改善手法では捉えきれなかった非効率を定量化できることが、プロセスマイニングの最大の価値だと評価されています。
プロセスマイニングで「手戻りゼロ」を目指すアプローチ
プロセスマイニングによって手戻りを削減するためには、以下の戦略的アプローチが効果的です:
1. KPI設計に「再作業率」や「逸脱頻度」を組み込む
プロセス分析の際に、全体効率だけでなく「どのステップで、何度、差し戻しが発生しているか」を定量化し、継続的にトラッキングすることが重要です。業務の健全性を測る指標として、再作業率を明確に位置づけることで、組織全体の改善意識を向上させることができます。
2. プロセスのバリアント(変異パターン)を把握する
同じ業務プロセスでも、部署や担当者によって異なる実行パターンが存在します。Celonisなどの高度なツールでは、このバリアント分析が可能で、標準化されていない業務フローや属人化の実態を明確に把握できます。手戻りが多発するバリアントを特定し、標準プロセスへの統一を図ることが重要です。
3. 改善アクションまで自動で提案・実行する
CelonisのExecution Management System(EMS)では、分析結果をもとに改善アクションの提案だけでなく、システム上でのワークフロー自動化も実現できます。手戻りが発生しやすいポイントに自動チェック機能を組み込んだり、承認フローを最適化したりすることで、根本的な解決を図ることが可能です。
4. リアルタイム監視による予防的対応
手戻りが発生してから対処するのではなく、手戻りが起こりそうな兆候をリアルタイムで検知し、事前に介入することで、より効果的な改善を実現できます。アラート機能を活用し、異常なパターンを早期発見することが重要です。
結論:プロセスマイニングは「見えない手戻り」を可視化する最強の武器
手戻りコストは、企業の競争力を蝕む見えないコストです。属人化された現場の判断、形骸化した業務フロー、システム間の連携不備――こうした課題を根本から解決するには、客観的なデータ分析が不可欠です。
プロセスマイニングは、現実に即した業務改善を促すための強力な武器となります。再作業を減らし、フローを最適化し、従業員のストレスを軽減することが、結果的に企業全体のパフォーマンス向上につながるのです。
特に、年商100億円以上の企業においては、手戻り削減による効果は絶大です。わずか数パーセントの効率改善でも、年間数千万円から数億円の価値創出につながる可能性があります。「手戻りは仕方がない」という固定観念を捨て、データドリブンなアプローチで根本解決に取り組むことが、真のDX推進への第一歩となるでしょう。
よくある質問(Q&A)
-
プロセスマイニングで本当に手戻りは減るの?
-
はい。実データに基づく分析により、再作業や逸脱の原因が可視化され、的確な改善策を講じることが可能になります。多くの企業で30%以上の手戻り削減効果が実証されています。
-
再作業の発生頻度はどうやって測定するの?
-
システムのイベントログに記録された処理の流れを基に、同一ケースで繰り返し発生するアクティビティや、標準フローからの逸脱パターンを自動検出することで算出可能です。
-
導入にはどの程度の期間が必要?
-
ディスカバリーワークショップを活用すれば、約1ヶ月で改善ポイントの特定が可能です。本格導入は規模により異なりますが、3-6ヶ月程度が一般的です。
ご興味のある方はこちら
【無料相談受付中】
「どの業務でプロセスマイニングを始めるべきか悩んでいる」「手戻りを減らすために、まず何から始めればいいのか分からない」そんなお悩みがあれば、お気軽に専門コンサルタントまでご相談ください。
プロセスマイニング導入のステップについて詳しく知りたい方は → 導入プロセス
Celonisの具体的な機能について詳しく知りたい方は → Celonis


