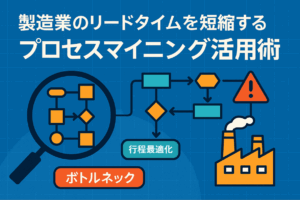プロセスマイニングによるKPIモニタリングの設計手法
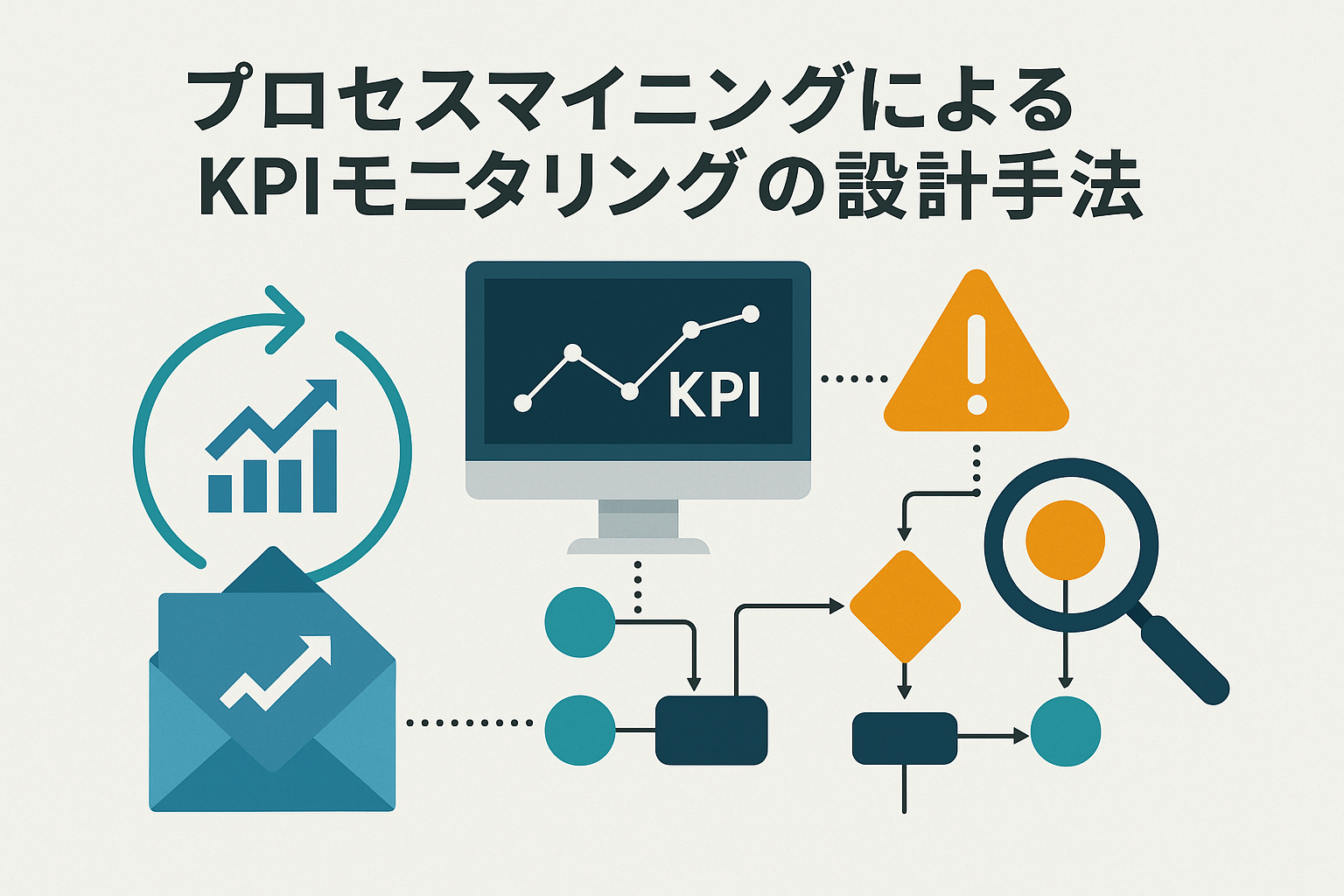
なぜ今、KPIモニタリングにプロセスマイニングが必要なのか?
企業が成長と競争優位を維持するためには、業務の可視化と定量的な管理が不可欠です。特に、KPI(重要業績評価指標)のモニタリングは経営判断の根幹を支える手法ですが、その設計や運用において多くの企業が課題を抱えています。データがサイロ化され、指標の算出に時間がかかる。異なる部門で定義が食い違う。あるいは、結果の乖離原因が特定できないままレポーティングだけが積み重なる――。
こうした課題を根本的に解決する手段として注目されているのが、プロセスマイニングによるKPIモニタリングの再設計です。特に、Celonisのような先進的なプラットフォームを活用することで、KPI監視と業務プロセスをリアルタイムに連携させ、改善インサイトを得ることが可能になります。
本記事では、KPI監視の課題を掘り下げながら、プロセスマイニングを活用したKPIモニタリングの具体的な設計手法と導入のポイントを詳述します。
プロセスマイニングとは何か?
プロセスマイニングとは、ERP(基幹業務システム)やCRM、ワークフロー管理システムに蓄積された「イベントログ(業務履歴)」を解析し、業務プロセスの実態を可視化・分析・改善する技術です。従来の手作業による業務分析とは異なり、実際のシステムログから客観的なプロセスの流れを抽出し、ボトルネックや逸脱を特定することができます。
特にCelonisのような先進プラットフォームでは、業務プロセスを「デジタルツイン」として再現し、指標連携したモニタリング・分析・改善のサイクルを自動化できます。
KPIモニタリングの従来課題
1. KPIの定義がプロセスと断絶している
多くの組織ではKPIがExcelやBIツールで個別に集計され、業務プロセスとの因果関係が見えづらい状況にあります。そのため、KPIの変動が発生しても、どの工程や部門に起因するのかが分からず、改善施策の特定が困難になります。
2. データ収集・集計の遅れ
従来はKPIレポートを月次・週次で集計し、経営会議に提出する形式が主流でした。この集計プロセスには時間がかかり、リアルタイム性に欠け、迅速な意思決定を妨げる要因となっています。
3. 改善アクションとの連動が弱い
KPIが悪化しても、その場でアクションにつながらないことが多く、PDCAサイクルが形骸化してしまいます。「見える化」にとどまり、「改善の実行」まで到達しないケースが散見されます。
プロセスマイニングを活用したKPI監視の設計手法
KPIと業務プロセスの統合設計
KPI監視において最も重要なのは、KPIを単なる数値指標ではなく、「プロセスの健全性を測るセンサー」として位置付けることです。そのためには、KPIをイベントログと連携させ、業務のどの工程と関係しているかを明確にする必要があります。
Celonisでは、PQL(Process Query Language)を用いることで、KPI定義を業務イベントに基づいて正確にトレースできます。例えば、「受注から出荷までのリードタイム」というKPIを設定する場合、受注登録から出荷完了までの各ステップでのタイムスタンプを自動的に計測し、異常値や遅延の発生箇所を特定することが可能です。
リアルタイムモニタリングダッシュボードの構築
KPI監視の効果を最大化するためには、リアルタイムでの変動監視とアラート機能が不可欠です。Celonis EMSでは、KPIと紐づいたプロセスの可視化とアラート通知が可能です。
具体的には、設定した閾値を超過した際の自動通知、プロセス内のボトルネックの可視化、さらには改善提案の自動生成まで実現できます。例えば、製造業における「製品品質KPI」が悪化した場合、どの生産ラインのどの工程で問題が発生しているかを瞬時に特定し、担当者に改善アクションを提案します。
KPI変動の原因分析(ルートコーズ分析)
従来のBIツールでは困難だった「KPI変動の根本原因分析」を、プロセスマイニングでは効率的に実現できます。Celonisでは、KPIの変動要因をプロセスデータから自動抽出する機能があり、属人的な分析に依存せず、改善の打ち手を明確にできます。
例えば、「顧客満足度KPI」が低下した場合、顧客対応プロセスのどの段階で問題が発生しているか(問い合わせ受付、担当者割り当て、回答作成、承認プロセスなど)を特定し、具体的な改善ポイントを提示します。
実際の成功事例に学ぶ:KPI監視の進化
事例1:製造業A社の在庫管理KPI改善
A社では「在庫回転率の改善」を目的にプロセスマイニングを導入しました。従来は月次で算出していた在庫回転率を、リアルタイムで監視するシステムを構築。その結果、出荷遅延の主要因が特定ベンダーの納品遅れに起因することが判明し、サプライヤ評価基準を見直すことでKPIが20%改善されました。
事例2:金融業B社の顧客対応KPI最適化
B社では「顧客対応満足度」のKPIが想定より低迷していました。プロセスマイニング分析により、特定の申込処理フローにおける再入力工数の多さが原因と判明。ワークフロー改修により、顧客満足度スコア(CSAT)が15ポイント向上しました。
これらの事例が示すように、プロセスマイニングによるKPI監視は、従来の「結果を見る」アプローチから「プロセスを改善する」アプローチへの転換を可能にします。
専門家・公的機関の知見
プロセスマイニング研究の第一人者であるWil van der Aalst教授は、「KPIは業務の出力にすぎず、その背後にあるプロセスを理解せずして改善はありえない」と指摘しています。また、IEEE Process Mining Manifestoにおいても、「プロセスマイニングは、パフォーマンス管理とコンプライアンスの要件を統合的に支援する新しい枠組みである」と位置づけられています。
これらの学術的裏付けが示すように、プロセスマイニングによるKPI監視は、単なるトレンドではなく、経営管理の新たなスタンダードとなりつつあります。
結論:KPIは「見る」から「動かす」へ
プロセスマイニングによるKPIモニタリングの再設計は、単なる数値の可視化を超え、業務と経営のダイナミックな連携を可能にします。リアルタイムのデータ連携、アクションにつながる原因分析、業務へのフィードバックループ――これらを兼ね備えたKPI設計は、もはや「理想論」ではありません。
企業がこれからの時代を勝ち抜くためには、KPIを単なる指標ではなく「組織の感覚器官」と捉え、その設計から見直すことが不可欠です。プロセスマイニングによるKPI監視の導入は、その第一歩となるでしょう。
よくある質問(Q&A)
-
KPIとプロセスマイニングの連携にはどんな準備が必要?
-
KPIの定義をイベントログに落とし込み、プロセスとの関係性を明示する必要があります。具体的には、現在のKPI算出方法を見直し、どの業務ステップから生成されるデータを使用するかを明確化することから始まります。Celonisではこれをプロセスクエリ言語(PQL)で実装できます。
-
プロセスマイニングを導入してすぐに効果は出ますか?
-
部分導入でも特定のKPIに対して数週間以内に効果が見られるケースがあります。まずは重点KPIに絞って始めるのが効果的です。完全な効果を得るためには、データ整備とプロセス改善の実行フェーズを経て、通常3-6ヶ月程度を要します。
-
現行のBIツールでは代替できないのですか?
-
BIツールは結果の可視化には優れていますが、プロセスとの因果関係を発見するには限界があります。プロセスマイニングは、KPIの変動原因を業務フローレベルで特定し、具体的な改善アクションまで提案できる点で差別化されています。両者は補完関係にあり、統合的に活用することで最大の効果を発揮します。
プロセスマイニング導入のステップについてはこちら → https://flr-process.com/celonis/process/
次のステップをお考えの方へ
KPIとプロセスの真のつながりを明らかにし、データドリブンな業務改善を実現したい企業様は、ぜひ無料相談をご利用ください。貴社の現状に合わせたプロセスマイニング活用戦略をご提案いたします。組織の「見える化」から「改善の実行」まで、一歩先を行くKPI管理手法をともに構築しましょう。