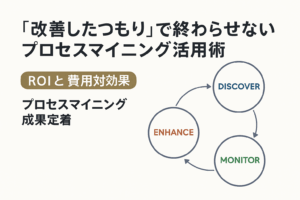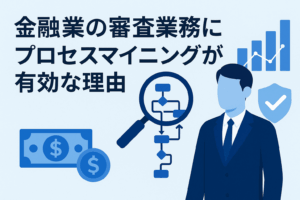プロセスマイニングの「継続運用」に必要な組織体制とは?

なぜ今、プロセスマイニングの運用体制が重要なのか?
プロセスマイニングは、企業の業務プロセスを可視化し、改善のための具体的な示唆を与えるツールとして注目を集めています。しかし、導入企業の多くが直面するのが「PoC(概念実証)は成功したが、その後の活用が続かない」という課題です。
この問題の本質は、技術的な課題ではなく、プロセスマイニング 運用体制が組織に根付いていないことにあります。本記事では、プロセスマイニングを企業活動の一部として定着させるために必要な組織体制について解説します。
プロセスマイニング導入後に直面する「継続性」の壁
多くの企業が直面する課題は、分析人材の不足と属人化です。プロセスマイニングツールは、ERPやCRMのイベントログから業務プロセスを可視化しますが、データを読み解き改善提案を行うには、業務理解とデータ分析の両面に精通した人材が不可欠です。
現実には、この役割が一部の担当者に集中し、属人化する傾向があります。担当者の異動や退職で、せっかく構築した分析環境やノウハウが失われてしまうのです。
また、プロセスマイニングの真価は複数部門での横断的な活用によって発揮されます。しかし、部門間で目的やKPIが異なり、データの整備状況にもばらつきがあるため、部門展開が進まないケースが少なくありません。
継続運用を実現する組織体制モデル
CoE(Center of Excellence)の設置が鍵
CoE(Center of Excellence)とは、プロセスマイニングの知見を集約し、各部門への展開や技術支援を担う専門チームです。先進企業の成功事例では、このCoEの存在が継続運用の鍵となっています。
CoEの主な役割:
- ツールの運用・保守:安定稼働の維持と技術的問題への対応
- 分析人材の育成:社内トレーニングプログラムの企画・実施
- 部門連携の促進:ユースケースの発掘と導入支援
- ガバナンスの確立:データ活用ルールとセキュリティ管理
CoEは情報システム部門や業務改革部門に設置されることが多いですが、経営企画部門に置くことで全社的な視点を持たせる企業もあります。
ハイブリッド型運用体制
より成熟した運用体制として、中央統括型CoEと部門分散型チームを組み合わせたハイブリッドモデルが注目されています。各部門に小規模な分析チームを配置しつつ、中央のCoEが全体の戦略・ガバナンスを担う形です。
部門ごとのスピード感と現場密着型の改善活動を維持しながら、組織全体の整合性も確保できる点が特徴です。年商100億円以上の企業では、このハイブリッド型が有効に機能します。
実践に学ぶ:継続運用を支える仕組み
ケーススタディ1:製造業における全社展開モデル
ある製造業では、調達部門でプロセスマイニングを導入し、在庫回転率の改善に成功しました。その後、専任チームをCoEとして正式に設置し、営業・経理・品質管理など全社へと段階的に展開しています。
成功のポイントは、定例でのユースケース共有会の開催です。部門を超えて成功体験を共有する文化が、プロセスマイニングの社内定着を加速させました。最初の成功事例が次の展開への推進力となり、組織全体の改善活動が活性化しています。
ケーススタディ2:人材育成プログラムの標準化
あるサービス業では、プロセスマイニング導入初期からCoEを設け、業務部門から選抜したメンバーに対して「分析スキル育成プログラム」を実施しています。
Celonis Academyの教材をベースに自社用にカスタマイズし、現在では全社で20名以上の分析担当者が継続的に改善提案を行う体制を構築しました。さらに、スキルの標準化とローテーション制度を導入することで、属人化を防いでいます。
分析人材の育成とスキル標準化
プロセスマイニングの運用体制において、最も重要な要素が分析人材の育成です。
必要なスキルセット:
- データ分析スキル:イベントログの理解、統計的手法の基礎
- 業務理解力:自社の業務プロセスへの深い理解
- コミュニケーション能力:分析結果を経営層や現場に伝える力
- 技術的知識:PQL(Process Query Language)などツール固有のスキル
効果的な育成には、段階的なトレーニング、実践的な演習、メンター制度、継続的な学習機会の提供が重要です。Celonis Academyのような公式トレーニングプログラムを活用することで、体系的なスキル習得が可能になります。
部門展開を成功させるポイント
部門展開を円滑に進めるには、初期段階で明確な成功事例を作ることが重要です。最初の導入部門で目に見える成果(コスト削減額、工数削減率など)を上げることで、他部門の関心と協力を引き出すことができます。
横展開のための効果的な仕組み:
- 定例共有会:月次または四半期ごとのベストプラクティス共有
- 社内ポータル:成功事例、分析テンプレート、FAQの情報集約
- ハンズオン研修:実際のツール操作を通じた実践的トレーニング
詳細な導入プロセスを文書化することで、他部門への展開がスムーズになります。
経営層のコミットメントの重要性
プロセスマイニングの運用体制を成功させるには、経営層の強力なコミットメントが不可欠です。CoEには経営層からエグゼクティブスポンサーを任命し、戦略的方向性の提示、リソースの確保、部門間調整を担ってもらうことが重要です。
また、データガバナンス(個人情報保護、アクセス権限管理)、プロジェクトガバナンス(優先順位付け、予算管理)、成果評価(KPI設定、ROI算出)といった明確なガバナンス体制の整備も必要です。
充実したサポート体制を活用しながら、自社に適したガバナンスの仕組みを構築していくことが重要です。
結論:持続的価値を生み出す組織づくり
プロセスマイニングを単なる分析ツールにとどめず、企業の競争力強化に資する「改善の仕組み」へと昇華させるには、プロセスマイニング 運用体制の整備が不可欠です。
成功のポイントは以下の3つです:
- CoEの設置:知見の集約と全社展開を推進する専門チーム
- 分析人材の育成:属人化を防ぎ、継続的な改善を実現する人材基盤
- 部門横断の協業:成功事例の共有と段階的な展開
技術やデータだけでなく、「組織」と「人」に投資することこそが、持続的な価値創出につながります。プロセスマイニングの可視化から実行までの一連の流れを理解し、自社に適した運用体制を構築することで、真の業務改革が実現できるのです。
よくある質問(FAQ)
Q1. CoEはどの部門に設置するのが適切ですか?
A1. 情報システム部門や業務改革部門に設置するケースが一般的です。ただし、経営企画部門に置くことで全社的な視点を持たせることも有効です。重要なのは、経営層の直接的な支援を受けられる位置づけにすることです。
Q2. 分析人材にはどのようなスキルが求められますか?
A2. データ分析やBIツールの活用経験に加え、業務理解力と課題設定能力が重要です。技術的にはPQLのようなツール固有のスキルも有効です。最初から完璧なスキルセットを求めるのではなく、継続的な育成プログラムを通じて段階的に能力を高めていくアプローチが現実的です。
Q3. 部門展開を進める際のコツは?
A3. まず初期段階で明確な成功事例を作ることが重要です。その成果を他部門へ積極的に共有し、定例の情報交換会やハンズオン研修を通じて横展開を図ります。各部門の固有の課題に合わせてカスタマイズすることで、導入へのハードルを下げることができます。
次のステップへ
「導入したものの活用が続かない」「一部門にとどまっている」とお悩みの企業様へ。
プロセスマイニングの真価は、継続的な運用によって初めて発揮されます。まずは、貴社に適した運用体制のあり方を一緒に考えてみませんか?
プロセスマイニングの基本的な理解を深めたい方は、プロセスマイニングとはのページをご覧ください。また、具体的な機能や活用方法については、Celonis製品ページで詳しく解説しています。
無料相談や資料請求はこちら → https://flr-process.com/
貴社の業務改革を、確かな運用体制とともに実現するお手伝いをさせていただきます。