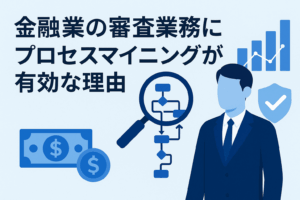本部と現場の分断をつなぐプロセスマイニングの設計アプローチ

組織融合を実現する、データ駆動型の新アプローチ
「本部は理想論を振りかざし、現場は疲弊している」――このような声は珍しくありません。本部と現場の組織内コミュニケーション断絶が、DXやプロセス改善の最大の障壁となっています。
この課題に対して注目されているのが「プロセスマイニングによる組織融合」です。本記事では、本部と現場の情報共有と意思一致を実現する設計アプローチを解説します。
本部と現場の分断が生まれる構造的背景
目に見えない壁の正体
多くの企業で、本部と現場の分断は単なる「コミュニケーション不足」では片付けられません。第一にKPIの不一致があります。本部は売上や利益率を重視する一方、現場は処理件数や納期遵守率で評価されます。この評価軸のズレが分断を生みます。
第二に意思決定の非対称性です。戦略は本部で決定され、現場は実行する立場に置かれる構造が、現場の改善提案を吸い上げにくくしています。第三に情報の断絶があります。現場の問題が本部にリアルタイムで伝わる仕組みがないのです。
従来手法の限界
これまでの会議体や業務フロー図には本質的な限界があります。会議は属人的で断片的、業務フロー図は「理想のプロセス」であり、実態とのギャップを可視化できません。現場の独自の工夫や緊急対応を捉えられないことが最大の弱点でした。
プロセスマイニングが実現する組織融合
「事実ベース」が生み出す共通言語
プロセスマイニングとは、ERPなどのシステムに記録されるイベントログから、業務プロセスの実態を可視化・分析する技術です。従来のBPMが理論モデルに依存するのに対し、実際のデータに基づく客観的な分析を可能にします。
この「実態ベース」が組織融合の鍵です。本部と現場が「どちらが正しいか」ではなく、全社共通の事実をベースに対話できるからです。CelonisのようなExecution Management Systemは、プロセスのギャップを明らかにし、AIによる改善策を提案することで、組織全体の業務遂行能力を向上させます。
共通KPIで全社最適を実現
組織融合の第一歩は、部門横断の共通KPI設計です。サイロ化された部門別指標ではなく、エンドツーエンドのプロセスKPIを設定します。たとえば「受注から出荷までのリードタイム」や「問い合わせ対応の完了率」など、プロセス全体に関わる指標です。
プロセス可視化ツールで、これらをダッシュボードで一元管理すれば、本部と現場が同じゴールに向かって協働できます。ある食品メーカーでは、調達から出荷までを統一KPIで管理した結果、部門連携が劇的に改善し、ボトルネックの所在が明確になりました。
現場の知恵を全社に展開
標準プロセスとは異なる現場独自のやり方(バリアント)を、単なる逸脱として矯正するのではなく、客観的に評価することが重要です。ある製造業では、複数工場の出荷プロセスを分析した結果、ある工場の独自フローが最も効率的と判明し、これを全社標準に採用してリードタイムが15%短縮されました。
現場の創意工夫を可視化し、ベストプラクティスとして横展開するアプローチは、組織融合を促進します。現場が評価される実感を持つことで、改善提案も活発化するのです。
組織融合を実現する設計と導入のポイント
意思決定のトレーサビリティを担保する
本部と現場の意思一致を促すには、判断の履歴を残すことが重要です。AI分析機能では、プロセス異常検知時の対応措置や判断理由を「アクションログ」として記録できます。このトレーサビリティが部門間の信頼形成につながり、組織融合の土台となります。
段階的な導入ステップ
組織融合を目的とした導入は、段階的なアプローチが効果的です。導入プロセスでは、まずパイロットプロジェクトで本部と現場が共同分析する経験を積みます。次にディスカバリーワークショップで関係者の理解を深め、最後に専門サポートを活用しながら全社展開します。
成功の3つのカギ
第一に経営層のコミットメントです。組織融合は文化変革を伴うため、経営トップが「事実ベースの対話」を推進する姿勢が不可欠です。第二に現場の巻き込みで、監視ではなく支援のツールであることを明確にします。第三に継続的な改善サイクルの確立で、データ分析と改善を繰り返すことで真価を発揮します。
実際の成果事例
ある製造業では、生産計画部門と製造現場の間にコミュニケーション断絶がありました。プロセスマイニングで計画から製造完了までを可視化した結果、計画変更が現場に与える影響が数値化され、両部門が週次でデータを見ながら協議する文化が生まれました。計画変更回数が40%減少し、現場の残業時間も25%削減されました。
また小売チェーンでは、本部の仕入戦略と各店舗の販売実態にズレがありました。リアルタイムデータ連携により在庫状況と販売動向を共有し、本部が柔軟に仕入調整できるようになった結果、欠品率35%低下と廃棄ロス20%削減を同時に実現しました。
よくある質問(Q&A)
Q1. プロセスマイニングの導入にIT部門の全面支援は必須ですか?
A1. 初期のデータ接続にはIT部門の協力が必要ですが、最近のツールはノーコード化が進み、業務部門主導でのPoC(概念実証)も可能です。特にCelonisは直感的なインターフェースを提供しています。
Q2. 本部と現場でKPIの優先度が違う場合、どう調整すればよいですか?
A2. エンドツーエンド視点での共通KPI設計が鍵です。一つのKPIが複数の部門にとって意味を持つように設計することで、自然と協力体制が生まれます。多次元分析機能を使えば、同じデータを異なる視点から見ることができます。
まとめ:組織融合の鍵は「見える化」と「共通言語」
本部と現場が一枚岩となるには、感覚ではなく事実に基づいた対話が必要です。プロセスマイニングは組織内の情報断絶を乗り越える共通言語を提供し、部門横断の意思一致と協働を促進します。
重要なのは、プロセスマイニングを単なる可視化ツールではなく、組織文化を変革する触媒として位置づけることです。データを共有し、事実に基づいて議論し、継続的に改善するサイクルを組織に根付かせることで、真の組織融合が実現します。
次のステップ:無料相談のご案内
「本部と現場の情報共有をどう進めればよいか」「プロセスマイニングが自社に適用できるか知りたい」――そのようなお悩みをお持ちでしたら、まずはお気軽にご相談ください。
貴社の業務プロセスをお伺いした上で、最適なプロセスマイニング導入設計を専門家が無料でご提案いたします。ディスカバリーワークショップで、貴社のプロセス課題を一緒に洗い出してみませんか? 本部と現場が一体となって業務改革を進めるための第一歩を、私たちがお手伝いします。