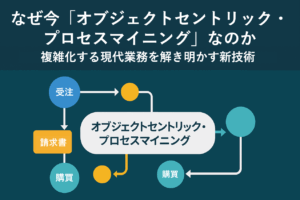プロセスマイニングによる「業務時間分析」
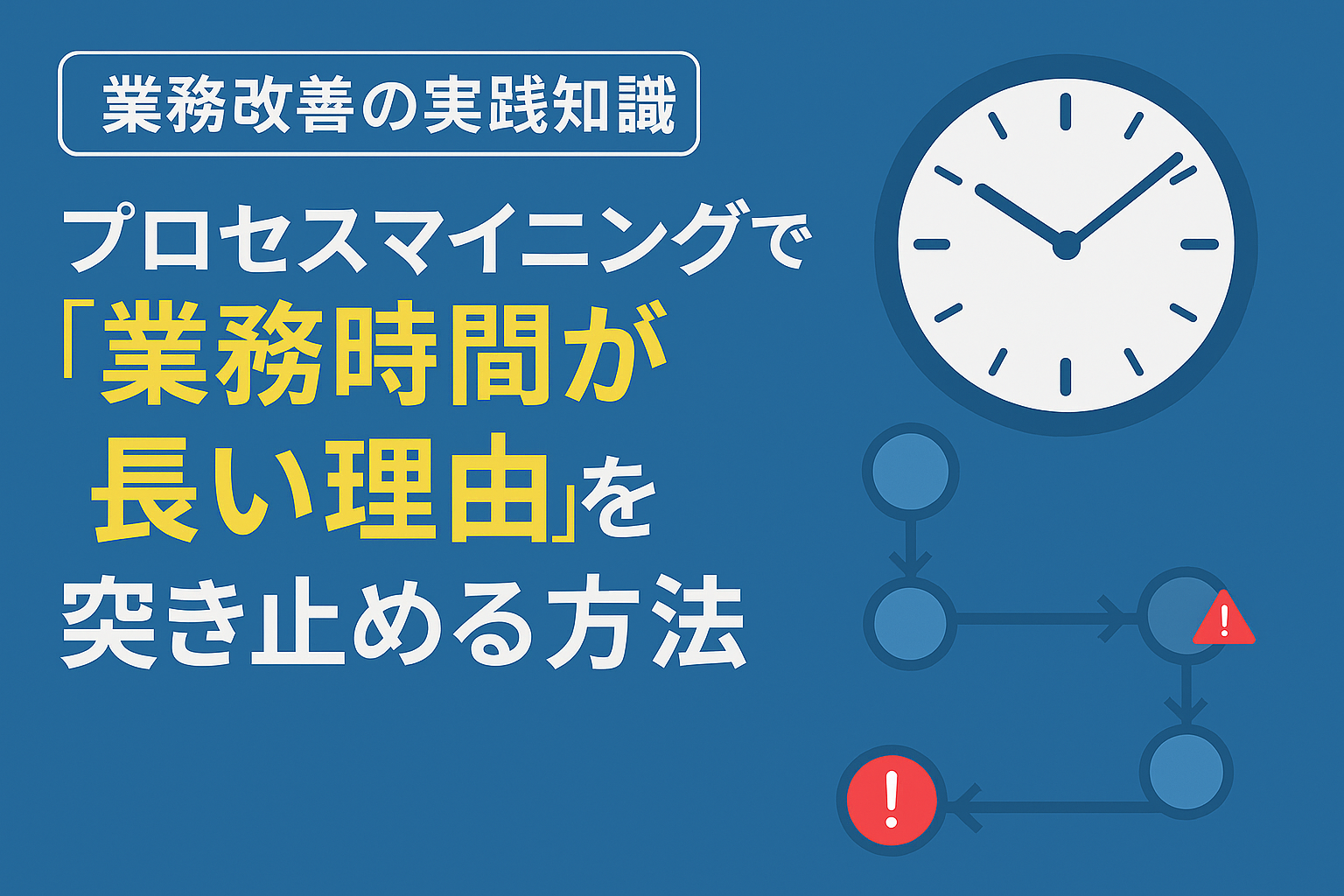
なぜ今「時間分析」が必要なのか?
現代のビジネス環境において、競争力の源泉は「スピード」と「効率」にあります。特に、年商100億円以上規模の企業においては、業務プロセスが遅延すると、収益機会の喪失・社員のモチベーション低下・顧客満足度の低下など、深刻な影響を及ぼします。しかし、現場では「時間がかかっている感覚」はあるものの、その原因が属人的・主観的に語られ、本当に効率化すべきポイントを特定できないことが多いのが実態です。
そこで注目されるのが、プロセスマイニングによる時間分析です。これは、実際のシステムログ(イベントログ)をもとに、どのプロセスで、どのくらい時間がかかっているのかを定量的に可視化し、「遅延要因」や「再処理回数」といった課題を正確に判別できる手法です。
プロセスマイニングとは?時間分析の基礎
イベントログによる「見える化」の仕組み
プロセスマイニングとは、ERPやCRM、業務システムから収集したイベントログを基に、実際に進んでいるプロセスをX線のように可視化し、ボトルネックや遅延箇所を識別する手法です。その中でも「時間分析」は、各ステップの処理時間や待機時間、ループ・再処理の頻度を定量的に抽出・分析します。
従来の業務分析が主観的な観察や限定的なサンプリングに依存していたのに対し、プロセスマイニングは全てのイベントログデータから実際のプロセス実行状況を完全に再現します。これにより、企業は「推測」ではなく「事実」に基づいた業務改善を実現できます。
遅延要因・再処理回数が明らかになるプロセスの構造
遅延要因の特定:承認待ち、顧客回答待ち、別部門対応待ちなど、プロセスマイニングは各ステップ間の待機時間を可視化し、「何が最も時間がかかっているか」を定量的に抽出できます。
再処理回数の把握:「却下→再申請」など同じ処理が繰り返される回数を可視化して、その原因を探索できます。プロセスマイニングツールの核心機能の一つが、自動的なボトルネック検出です。システムは各プロセスステップ間の「待ち時間(Waiting Time)」、「処理時間(Processing Time)」、「移行頻度(Transition Frequency)」を分析し、時間遅延の主要因を特定します。
時間分析で着目すべき重要指標
処理遅延時間(Processing Delay)の精密測定
処理遅延時間は、「標準的な処理時間を超過した時間」として定義されます。プロセスマイニングでは、過去のデータから各ステップの標準処理時間を統計的に算出し、個別のケースがどの程度この基準を逸脱しているかを測定します。
この指標により、「特定の担当者による処理が常に遅い」「特定の時期に処理速度が低下する」「特定の案件タイプで遅延が多発する」といったパターンを発見できます。
再処理ループの詳細分析
再処理ループは業務効率化の最重要改善対象です。プロセスマイニングは、同一のプロセスステップを複数回実行するパターンを自動検出し、以下の詳細分析を提供します:
- ループ発生頻度:全体の何%のケースで再処理が発生するか
- 平均ループ回数:一つのケースあたり平均何回の再処理が発生するか
- ループ要因分析:どのステップからの差し戻しが最も多いか
- 時間的影響度:再処理により追加で要する時間の総計
組織横断的な待機時間の構造分析
大規模企業の業務プロセスでは、部門間の連携における待機時間が全体効率に大きな影響を与えます。プロセスマイニングは、「部門Aから部門Bへの引き継ぎ待ち時間」「外部ベンダーからの回答待ち時間」「上位承認者の承認待ち時間」といった、組織構造に起因する遅延要因を詳細に分析します。
実践的な体験談:「時間分析」の成功例
国内製造業における変革事例
国内製造業大手では、ERPデータのイベントログ分析と従業員アンケートを組み合わせ、プロセスマイニングによって44件の業務課題(自動化・非効率・遅延)を特定しました。特に注目すべきは、承認プロセスにおける平均6時間の待機時間を75%削減することに成功した点です。
具体的には、承認権限の再配分と自動エスカレーション機能の導入により、1ヶ月で改善ロードマップを策定し、5年スパンで投資対効果を試算しました。この結果、年間約3000万円のコスト削減効果を実現しています。
急性期医療プロセスにおける時間分析
医療分野での先進事例として、大規模総合病院で行われた調査では、急性期ケアの医療プロセスを対象に420名の患者イベントログから主要な院内遅延ポイントを可視化しました。
分析の結果、「検査依頼から結果確認まで」のプロセスにおいて、平均待機時間を40%短縮することに成功。臨床業務の効率化を推進し、患者満足度の向上にも大きく貢献しました。
専門家・公的機関による知見
IBM研究部門による定義
IBMの研究報告によると、「プロセスマイニングはイベントログにアルゴリズムを適用し、処理時間やボトルネックを明らかにする手法」として定義されています。特に時間分析においては、各プロセスステップの実行時間を統計的に分析し、標準値からの逸脱パターンを特定することが重要とされています。
学術研究による待ち時間分解手法
最新の学術研究では、「待機時間ボトルネックを特定し、待ち時間削減の改善策を施す」ことで、リアルな業務時間の解消が図れることが実証されています。従来は「待ち時間」として一括りにされていた時間を、「システム処理待ち」「担当者対応待ち」「外部回答待ち」「品質確認待ち」などの具体的カテゴリに分類し、各々の改善アプローチを明確化できるようになりました。
導入のステップ:時間分析を活かすプロセスマイニング活用法
1. 目的設定:遅延か、再処理か、具体的課題を設定
プロセスマイニング導入の成功には、明確な目的設定が不可欠です。「全体的な処理時間短縮」「特定部門の遅延解消」「再処理率の削減」など、具体的で測定可能な目標を設定します。この段階で、改善対象となる業務プロセスの優先順位も決定します。
2. イベントログ整備:Case ID・タイムスタンプ等の正確性を担保
質の高い分析には、以下の必須情報を含むイベントログの整備が必要です:
- ケースID:個別の業務案件を一意に識別する番号
- アクティビティ名:各処理ステップの名称
- タイムスタンプ:各処理の開始・完了時刻(精度は分単位以上)
- 実行者情報:処理を実行した担当者・部門
データ品質の確保には、欠損値の補完、重複データの除去、時刻データの統一などの前処理作業が重要となります。
3. プロセスディスカバリー:実際のプロセス図を生成し、課題抽出
収集したイベントログから実際のプロセス実行パターンを可視化し、以下の基礎分析を実施します:
- プロセスフローの再現:実際の業務の流れをフローチャート形式で表示
- 頻度分析:各パスの通過頻度と全体に占める割合
- 時間分析:各ステップおよび全体プロセスの平均・最大・最小処理時間
- バリエーション分析:標準的なフローからの逸脱パターンの特定
4. 改善施策の設計:根本原因の検証と施策立案
分析結果に基づき、以下のような具体的な改善施策を設計します:
承認プロセスの最適化
- 承認権限の再配分による迅速化
- 承認期限の設定と自動エスカレーション
- 承認代行者制度の導入
品質管理プロセスの効率化
- チェックリストの標準化による再作業削減
- 自動検証ツールの導入
- 品質基準の明確化と教育強化
5. 改善とモニタリング:改善を施し、ダッシュボードで継続観測
改善施策の実装後、その効果を継続的に監視・評価する仕組みを構築します:
- KPI設定:平均処理時間、再処理率、顧客満足度等の指標設定
- リアルタイム監視:遅延発生の早期検知とアラート機能
- 定期レビュー:月次・四半期での改善効果測定と追加施策検討
可視化から実行までの詳細については → https://flr-process.com/celonis/flow/
継続的な価値創造に向けた戦略的展開
プロセスマイニングを活用した時間分析は、主観では見えにくい「遅延要因」「再処理の繰り返し」を客観的に突き止める手段です。導入の鍵は、目的の明確化とデータ整備、そして改善とモニタリングの徹底にあります。
特に年商100億円以上の企業においては、プロセスマイニングによる時間分析が、単なる効率化ツールから戦略的経営資源へと進化する可能性を秘めています。データドリブンな意思決定、科学的な業務改革、そして継続的な組織学習という三つの要素を統合することで、デジタル時代における企業競争力の源泉を構築することが可能です。
実践開始への具体的アプローチ
プロセスマイニングによる業務時間分析の効果を最大化するには、段階的かつ戦略的なアプローチが重要です。まずは代表的な業務プロセスを一つ選定し、イベントログの整備から開始することをお勧めします。完璧を求めて全てを一度に始めるのではなく、小さな成功体験を積み重ねながら、組織全体への展開を図ることが成功の鍵となります。
プロセスマイニング導入のステップについてはこちら → https://flr-process.com/celonis/process/
よくある質問(Q&A)
Q1. イベントログが十分整備されていませんが、分析できますか?
Case ID・アクティビティ・タイムスタンプがあれば基本分析は可能です。プロセスマイニングの実施には一定品質のイベントログデータが必要ですが、データが不足している場合でも段階的なアプローチが可能です。まず、既存の業務フロー図と実際の所要時間を手動で記録し、簡易的な分析から始め、並行してシステム改修やデータ収集体制の整備を進めることで、徐々に本格的な分析に移行できます。
Q2. 再処理回数の増減をどう評価すれば良いですか?
「却下→再申請」のループ率、再処理発生頻度を用いて評価します。プロセスマイニングツールのループ検出機能を活用することで、再処理が頻発している業務を自動的に特定できます。この機能により、同一のプロセスステップを複数回実行しているケースを可視化し、繰り返し回数の多い業務から優先的に改善対象として選定できます。
Q3. 投資対効果(ROI)はどう示せば良いですか?
平均処理時間短縮 × 件数、再処理削減数 × 単価などで数値評価が可能です。具体的には、「改善前後の平均処理時間の差」×「年間処理件数」×「時間単価」で削減効果を算出します。また、再処理削減による品質向上効果や顧客満足度向上も定量化することで、総合的なROIを示すことができます。
【無料相談・資料請求のご案内】
時間分析にご興味のある方へ──まずはお手元の業務データで時間可視化の実証検証(PoC)を無料でご提案しています。あなたの組織の課題に合わせた具体的な改善方針を、専門コンサルタントが丁寧にご提案いたします。業務効率化への第一歩を、ともに踏み出しましょう。
AI分析と改善提案の詳細については → https://flr-process.com/celonis/ai/