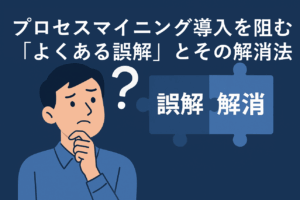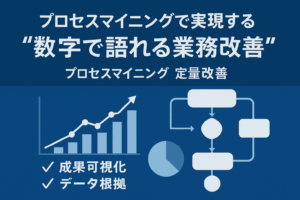ERP連携で失敗しないためのプロセスマイニング導入手順

企業の業務改善において「プロセスマイニング ERP連携」は、いまや欠かせないキーワードとなりつつあります。ERP(基幹業務システム)は企業の神経網とも言える存在ですが、その中に蓄積される膨大なイベントデータを最大限に活かせている企業はまだ多くありません。そこで注目されるのが、プロセスマイニングという新しい技術です。今回は、ERPとプロセスマイニングを連携させる際に失敗しないための導入手順について、具体的かつ実務的に解説します。
なぜ「プロセスマイニング ERP連携」が重要なのか
多くの企業では、ERPを導入しても「プロセスの全容が見えない」という課題に直面しています。ERPはトランザクションデータを中心に構築されており、プロセスの流れそのものをリアルタイムで可視化できるわけではありません。そこで、プロセスマイニングを組み合わせることで、ERPが記録するイベントログをもとに、業務のボトルネックや逸脱を客観的に把握し、改善につなげることが可能になります。
実際に、ある大手製造業ではERPのデータをもとに受注から出荷までのプロセスをプロセスマイニングで分析した結果、承認フローの遅延や無駄な差戻しが年間400時間以上発生していたことがわかり、ワークフロー改善で解消した事例があります(出典:「プロセスマイニング導入事例 2024」ITmedia)。
また、専門家であるWil van der Aalst教授(RWTH Aachen University)は「ERPのような情報システムが生み出すイベントデータは、プロセスマイニングにおける最も価値のある資源だ」と述べています。
導入前に押さえるべきデータ構造のポイント
ERPとプロセスマイニングを連携させる際に最も重要なのが「データ構造」の理解です。ERPに蓄積されるイベントログは、アクティビティ(処理内容)、ケースID(取引単位)、タイムスタンプ(発生日時)が三要素として含まれます。この三要素をプロセスマイニングで活用できる形に正規化することが不可欠です。
特にSAP ERPを例に取ると、テーブル構造が複雑であるため、抽出設定を行う前に「どのテーブルから、どの項目を取り出すか」を業務フローごとに設計する必要があります。Celonisのようなプロセスマイニングツールでは、この設計フェーズを支援するテンプレートが豊富に用意されています(参考:https://flr-process.com/celonis/tool/)。
データ抽出設定のベストプラクティス
ERP連携での失敗要因として多いのが、抽出設定の甘さです。例えば、必要なフィールドを抜き出したものの、結合条件が不十分でケースIDが分断され、プロセスマイニング上で「不完全なプロセスモデル」になってしまうケースです。こうした事態を防ぐには、以下のポイントを押さえる必要があります。
- ケースIDの一意性を保つ結合ロジックの定義
- データの更新頻度を考慮したインクリメンタル抽出の設計
- データ抽出後のクレンジング(異常値除去や項目の標準化)
CelonisのExecution Management System(EMS)のようにリアルタイム連携を前提とした仕組みを利用すると、更新データを差分抽出して高速に反映できます(参考:https://flr-process.com/celonis)。
実務で役立つ導入ステップ
ここからは、プロセスマイニングをERPと連携させるための実践的な導入ステップを整理します。
- プロセス可視化のゴール設定
改善したいKPI(納期遵守率、リードタイムなど)を明確化します。 - イベントデータの棚卸し
ERPに記録されているイベントログの構造とボリュームを棚卸しし、分析可能な粒度を把握します。 - 抽出要件の定義とPoC(概念検証)
まずは限定的なプロセスから試験導入し、データ構造や抽出設定の課題を早期に洗い出します。 - 本格導入と運用
全社プロセスに展開し、KPIモニタリングやプロセス改善の仕組みを定着させます。
これらの段階を踏むことで、ERPに閉じ込められていた価値あるデータを可視化し、企業競争力の強化に直結させることができます。
まとめと行動提案
プロセスマイニングとERP連携は、業務改善の次の一手として非常に強力です。しかし、データ構造や抽出設定を軽視すると失敗に陥りやすいのも事実です。今回ご紹介した導入手順を参考に、まずはPoCから始め、着実に成功への道を歩んでいただければと思います。
さらに詳しいステップや支援サービスについては、以下のページもご覧ください。
→ プロセスマイニング導入のステップについてはこちら